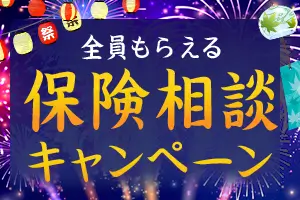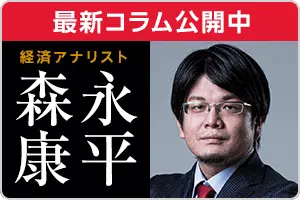国内最大級の保険選びサイト【保険市場】
 相談件数15万件突破!※2
アバターコンサルタントも指名できる満足度が高い
無料オンライン保険相談
相談件数15万件突破!※2
アバターコンサルタントも指名できる満足度が高い
無料オンライン保険相談
取扱保険会社97社・357商品から探す[2024/4/19 現在]
おすすめコンテンツ
最新のお知らせ
保険の種類から探す
保険料を見積もる
ランキングから探す
保険会社から探す
すべて見る
保険について知る・学ぶ
コラム一覧
すべて見る- 死亡保険コラム
- 医療保険・入院保険コラム
- がん保険コラム
- 女性保険コラム
- 学資保険コラム
- 個人年金保険コラム