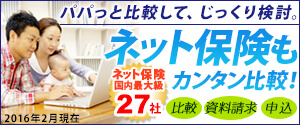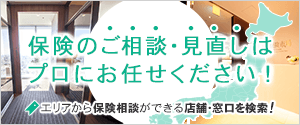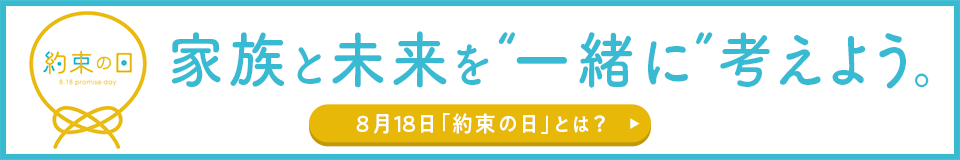がん保険ニーズが高まる2つの理由

がん治療が長引くと深刻なお金の問題に直面する
がん保険は、がんの保障に特化した保険で、近年、ニーズが高まっています。その理由は大きく2つ考えられます。
がんは生活習慣病の1つです。生活習慣病とは、食習慣や運動習慣、喫煙、飲酒などの生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている病気の総称で、不規則な生活習慣を長く続けるほど発症リスクが高くなります。
長寿大国となった日本ではがんの罹患者も増えています。国立がん研究センターがん対策情報センター「最新がん統計」(2010年11月30日更新)によると、今や日本人の2人に1人はがんにかかるというデータがあるくらいで、他人事ではない「自分事」の病気なのです。これが、1つ目の理由です。
厚生労働省の平成23年人口動態統計月報年計(概数)の概況(2012年6月5日発表)によると、1981年以来、がんは日本人の死因の第1位をキープし続け、年間30万人強の人ががんで亡くなっており、死に直結、あるいは死を連想させる恐怖の対象となっている病気です。
とはいえ、がんの診断・治療技術の進歩で早期発見して治療をすれば治る病気になってきています。
ところが、がんは再発や転移をする病気で治療は長引くことが多く、その間の治療費の自己負担や収入減・途絶など、がん患者とその家族は深刻なお金の問題と直面することになります。
最近では、健康保険適用外となる先進医療もあり、お金の問題はより深刻化しつつあります。これが2つ目の理由です。
がん保険は、診断給付金・入院・手術を基本的な保障として、通院や退院療養、先進医療などの保障をセットした商品で、商品ごとにセットされている保障は異なります。主に、がんの治療費に備えるために利用する保険です。
がんの治療費に備えるには、がん保険を利用する他に、死亡保障の保険や医療保険に、がんの保障を手厚くする特約をつける方法、あらかじめがんの保障をセットした医療保険に入る方法があります。
最近のがん治療は、通院のみで行うケースも増えているため、そのような治療でも給付金が出るタイプの商品を選ぶといいでしょう。
- がん保険選びの豆知識
- がんの治療方法は変わっている!
- かつてのがん治療は手術が中心でした。しかし、最近では、手術・放射線治療・抗がん剤治療を効果的に組み合わせた「集学的治療」が主流になっています。
- それにより、治療は通院で行われるケースが増えています。このため、従来のがん保険では、加入者が必要とする保障目的に合わなくなっています。
- 現在では、通院だけでも給付金が出る新型のがん保険が発売されるようになっています。
ファイナンシャルプランナー 小川 千尋
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
こちらの記事も参考に
掲載日:2020年3月30日
がん保険の選び方 ~厳選5ポイント~

ご自身に合ったがん保険を選ぶときに、チェックすべきポイントがたくさんあって悩んでしまわれる方は、がん保険を選ぶ際に考えるべきポイントを主な5つに絞り、そこからご自身に合った商品はどのようなものかを考えてみましょう。
- 終身型か定期型か
- がんの罹患リスクは、男女とも年齢と共に上がるため、50代・60代のことも考慮して、比較的保険料がお手頃な30代・40代のうちに、終身型のがん保険に加入するのも一案です。
- ただし、終身型は年齢が低いうちは定期型のがん保険より保険料が高くなりがちです。
- 支出を抑えたい方は、保障と収入のバランスを考えて加入を検討しましょう。
- 通院給付金・がん診断給付金が受け取れるか
- 近年のがん治療では、入院日数は減少し、通院が増えていることから、通院給付金が受け取れる商品の方が支えになるかもしれません。また、がん診断給付金で現金を受け取れると、治療のための費用や生活費など、いろいろな用途に使いやすいでしょう。
- 日額給付タイプか実損払いタイプか
- がん保険には、生命保険に多い「入院1日あたりいくら」という日額給付タイプと、損害保険に多い「がんの治療費を全額補償する」という実損払いタイプがあります。
- 実損払いタイプの保険なら、基本的に治療費の不足の心配はありませんが、近年はがん検診の受診により、がんの種類によっては早期発見および早期治療が可能となりつつあります。
- ご自身が求める支払いタイプを見極めましょう。
- 先進医療での治療費が支払われるか
- がん患者に施される陽子線治療・重粒子線治療の件数やがん罹患者数のデータをみると、先進医療を受けるがん患者数は少数であることが分かります。
- しかし、もし先進医療を受けるとなれば高額の治療費がかかること、また、がんの先進医療に関する保障は、特約の場合毎月数百円ほどの保険料で付加することが可能なことから、万一のため保障を付けておくのも一つの手段でしょう。
- 上皮内新生物の保障があるか
- 上皮内新生物(上皮内がん)は、上皮(皮膚や粘膜の表面、浅い部分)の内部にできるがんで、保障の対象外となる商品もあります。
心配な方は、診断給付金が出るものを選ぶ方が安心でしょう。
以上の主なポイントに注目して、ご自身に最適ながん保険選びに役立ててみてください。
こちらの記事も参考に
今すぐ相談したい方はこちら
![]()