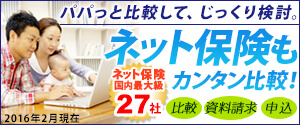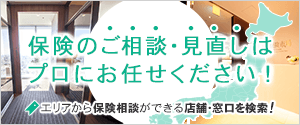資産運用に必要な数字 その3 ~為替
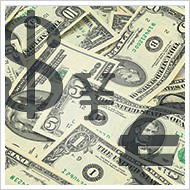
はじめに
「資産運用に必要な数字その3」では、「為替」についてみていきます。
2011年度から最近(2014年9月)の対ドル、対ユーロの円相場は表1のとおりです。
表1:円相場(対ドル・対ユーロ)
| 対ドル | 対ユーロ | |
|---|---|---|
| 2011年度 | 79.05 | 108.96 |
| 2012年度 | 82.89 | 106.73 |
| 2013年度 | 100.16 | 134.20 |
| 2014年1月 | 103.94 | 141.50 |
| 2月 | 102.13 | 139.32 |
| 3月 | 102.27 | 141.47 |
| 4月 | 102.56 | 141.63 |
| 5月 | 101.79 | 139.77 |
| 6月 | 102.05 | 138.75 |
| 7月 | 101.72 | 137.84 |
| 8月 | 102.96 | 137.13 |
| 9月 | 107.09 | 138.38 |
資料:日本経済新聞 景気指標欄(出所:日銀)を参考に執筆者作成
2011年と2014年9月の円相場を比較しますと、約3年間でドルは円に対して約35%上昇、ユーロは約27%上昇したことになります。
海外資産の運用では、債券利子や株式の値上がりよりも、為替変動が投資収益に大きく影響を与える場合があります。
以下、為替変動の要因となる数字や金融政策について、短期的な要因、中長期的な要因に分けてみていきます。
短期的な要因
短期的な為替の変動要因となる金融政策としては、各国中央銀行で発表される政策金利の動向があります(ユーロ圏ではECB(欧州中央銀行)が行います)。
一般的に、政策金利の引き上げはその国の通貨を上昇させる要因となり、引き下げは下落させる要因になります。
政策金利の引き上げには、景気の過熱を抑えるための引き上げと自国通貨の下落を抑えるための引き上げ等があります。要因については確認が必要です。
政策金利の引き下げの余地がなくなった場合に行われる政策として「量的金融緩和政策」があります。この政策は、中央銀行が市中銀行等の金融機関の保有する国債等を買い取ることによって、世の中に出回るお金の量を増やし景気を刺激する方法です。
最近の「量的金融緩和政策」の代表例としては、米国FRB(連邦準備制度理事会:米国の中央銀行にあたる機関)による「量的金融緩和(QE1~3)」と日銀による「異次元金融緩和政策」があります。
日本は「量的金融緩和」継続中ですが、米国の量的な金融緩和政策は、2014年1月から政策を終了する方向に舵を切りました。毎月の雇用統計やインフレ率等の数字を確認しながら、国債等の資産の買い入れ額を毎月減らしています。
「年内中には、量的金融緩和政策が終了し、来年後半には政策金利を徐々に引き上げていくだろう」と多くの市場関係者は考え、お金の流れが新興国から米国へ変わる可能性と、そのことにより起こる急激な為替変動(特に新興国通貨)リスクを警戒しています。
また、短期的な要因の中には、テロや紛争等に起因する「地政学的リスク」があります。
このリスクは数字に表すことができませんが、発生した場合、短期間に為替や株価等が大きく変動する要因になり得ます。新聞やネット等で世界情勢の確認をするようにしましょう。
2014年の例ですと、「ウクライナ」や「イラク・シリア」がそれにあたります。
中長期的な要因
中期的に為替を動かす要因としては、日本と他の国の金利差があります。
一般的に、同じような経済レベル、インフレ率の2国間で金利差が生じた場合、高い金利の国の通貨が上昇し、低い金利の国の通貨が下落します。
例えば、米国の景気が順調に回復し、FRBが政策金利を継続的に引き上げていく状況の中で、日本の金利が低いままですと、日米の金利差が徐々に拡大していきます。それによって円安・ドル高の方向に動くことが考えられます。
長期的には、2国間の国力の差が開いていくことで、為替に影響を与えることもあります。
国力の差をみる指標としてGDP(国内総生産)成長率があります。この指標は、IMF(国際通貨基金)等が発表しています。表2はIMFが発表した先進国の実績と見通しです。
表2:世界経済の実績と見通し(対前年比 単位:%)
| 実績 | 見通し | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| 世界経済 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
| 先進国 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| 米国 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 3.1 |
| 日本 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 |
| ユーロ圏 | -0.7 | -0.4 | 0.8 | 1.3 |
| ドイツ | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.5 |
| フランス | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
| イタリア | -2.4 | -1.9 | -0.2 | 0.8 |
| スペイン | -1.6 | -1.2 | 1.3 | 1.7 |
| イギリス | 0.3 | 1.7 | 3.2 | 2.7 |
| カナダ | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 |
資料:IMF 「世界経済見通し 改定見通し(2014年10月7日発表)」を参考に執筆者作成
表2は、IMFの資料から先進国の部分を抜粋しています。実際には、主要な新興国等の見通しも掲載され、レポート形式で定期的に発表されます。継続的に読むことで、その時々の各国の勢いを確認することができます。長期の為替見通しを立てる上で参考になるレポートです。
まとめ
資産運用は長期的なスタンスで行います。
IMFが発表するGDP見通しのレポート等を参考にしながら、中央銀行の金利政策や毎月発表される雇用や景気に関する統計資料、2国間の金利差の状況等、こまめに確認することで今後の為替トレンドについて考えていきましょう。

-
コラム執筆者プロフィール
恩田 雅之 (オンダ マサユキ) マイアドバイザー.jp®登録 - 1959年東京生まれ。
2004年3月にCFP®資格を取得。
同年6月、札幌にて「オンダFP事務所」を開業。
資産運用をテーマとした個人向けのセミナー講師や3級、2級ファイナンシャル・プランニング技能士取得の講師やライフプラン、金融保険関連のコラムやブログの執筆など中心に活動中。
ファイナンシャルプランナー 恩田 雅之
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
今すぐ相談したい方はこちら
![]()