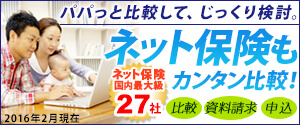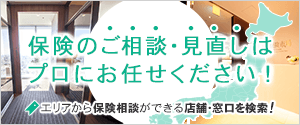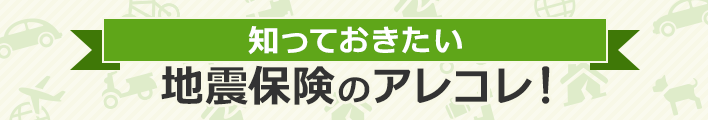
地震保険とは
最終更新日:2017年5月26日
はじめに
地震保険は、火災保険では補償されない「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害」を補償する保険になります。
以下、地震保険の特徴についてみていきましょう。
地震保険の特徴その1
地震保険は、政府と民間の損害保険会社が「地震保険に関する法律」に基づいて共同で運営している保険で、保険会社による商品内容や保険料の違いはありません。地震などによって一定額以上の巨大損害が生じた場合、本来保険会社が支払う保険金の一部を政府が再保険することで成り立っています。
また、被災者の生活の安定に寄与することを目的に作られた保険のため、補償の対象は居住用建物(居住のみに使用される建物および併用住宅)および家財(生活用動産)に絞られています。
例えば、以下のような家財は補償の対象外になります。
- 1.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車など
- 2.1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とうなど
- 3.稿本、設計書、図案、証書、帳簿、その他これらに類するもの
地震保険の特徴その2
地震保険は単独では契約できません。前提として、火災保険に付帯して契約することになります。なお、現在加入している火災保険に、途中から地震保険を付帯することも可能です。
保険金額は、火災保険の保険金額に対して30%~50%の範囲内で設定します。ただし、限度額の設定があり、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。
また、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分類された損害の程度によって、支払われる金額が異なります。
保険金額は時価額が限度となり、損害の程度により以下のように設定されています。
表1 損害の程度によって支払われる保険金の一覧
| 損害の程度 | 支払われる保険金 |
|---|---|
| 全損 | 保険金額の100%(時価額が限度) |
| 大半損 | 保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
| 小半損 | 保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
| 一部損 | 保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
なお、一部損に至らない損害や、門・塀・垣のみの損害に対しては、保険金が支払われません。
地震保険の特徴その3
地震保険の保険料は、建物の所在地(都道府県)と建物の構造により異なり、建物の構造は、イ構造、ロ構造の2つに分類されています。
- イ構造:主として鉄筋・コンクリート造の建物
- ロ構造:主として木造の建物
同一所在地で比較した場合の保険料は、イ構造の方が安く、ロ構造の保険料の約40%~60%になっています。
また、建物の免震・耐震性能に応じて4つの割引制度が設けられています。
所定の確認資料を提出することで、地震保険の保険料に対して10%~50%の割引率が適用されます。
表2 地震保険の割引制度
| 割引名 | 割引率 | |
|---|---|---|
| 建築年割引 | 10% | |
| 耐震診断割引 | 10% | |
| 耐震等級割引 | 耐震等級1 | 10% |
| 耐震等級2 | 30% | |
| 耐震等級3 | 50% | |
| 免震建築物割引 | 50% | |
なお、上記の割引制度は重複して適用を受けることはできません。
まとめ
以上、補償範囲、契約形態(火災保険とセット契約)、保険料など地震保険の特徴についてみてきました。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
地震保険の基本情報
知っておきたい地震保険のアレコレ!
今すぐ相談したい方はこちら
![]()