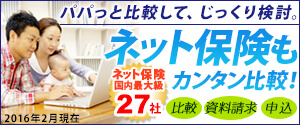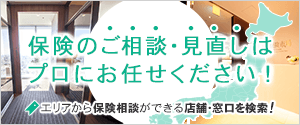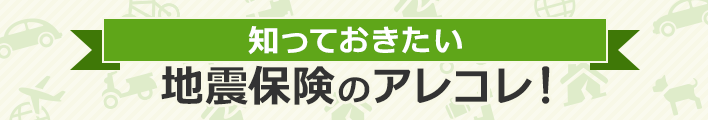
地震保険の値上げ
最終更新日:2017年5月26日
はじめに
地震保険の保険料は、損害保険料率算出機構が算出する基準料率に連動します。
地震保険の基準料率は、被害予測シミュレーションによる危険度計算に基づいて算出され、2014年7月の改定により、基準料率は全国平均で「+15.5%」引き上げられました。
その後、危険度計算を改めて行った結果、基準料率を全国平均で「+19.0%」の引き上げが必要な状況であることがわかりました。ただし、前回の改定から期間が短いため、今回の基準料率の引き上げは、3段階に分けて実施されることが、損害保険料率算出機構のホームページで公開されています。
以下、損害保険料率算出機構の「ニュースリリース」をもとに基準料率の改定についてみていきましょう。
基準料率引き上げ経緯
今回、基準料率算出に使用している各種基礎データ(震源モデル、地盤データ、被害関数)の更新を行うにあたり、「東北地方太平洋沖地震」のデータを震源モデルに反映しています。また、被害関数(揺れの大きさと揺れによる被害の関係)についても、東北地方太平洋沖地震などによる保険金支払実績を踏まえた改良を行っています。
なお、今回の引き上げ(+19.0%)に大きな影響を与えたのは、震源モデルの更新です。
2017年1月に第1回目の改定実施
2017年1月の改定では、基本料率(割引適用前の基準料率)のみの改定で、割引率などに変更はありません。
この改定での全国平均の引上率は、「+5.1%」です。
- 構造区分別の引上率
-
- ・イ構造(耐火建築物、準耐火関築物および省令準耐火建物など)…+5.1%
- ・ロ構造(イ構造以外の建物)…+5.2%
ただし、改定率は都道府県・建物の構造区分(イ構造、ロ構造)により異なり、最大引上率+14.7%、最大引下率-15.3%と地域により差が出ています。
- 構造区分別の改定率
-
- ・イ構造…最大引上率:+14.7%、最大引下率:-15.3%
- ・ロ構造…最大引上率:+14.6%、最大引下率:-11.3%
そのため、震源モデルの更新による影響が大きくない都道府県では、以下の要因により基本料率が引き下げとなっています。
- 1.被害関数の改良で、建物の耐震性能をより的確に反映した点。
- 2.損害区分を、現行の3区分から4区分に改正した点。(表1参照)
表1 損害区分と支払割合
| 改正前(3区分) | 2017年1月以降(4区分) | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 支払割合 | 区分 | 支払割合 |
| 全損 | 100% | 全損 | 100% |
| 半損 | 50% | 大半損 | 60% |
| 小半損 | 30% | ||
| 一部損 | 5% | 一部損 | 5% |
等地区分の変更
等地区分とは、都道府県を地震の危険度によって3つに分類することをいいます。
等地区分1が地震の危険度が一番小さく、数字が大きくなると危険度が大きくなります。
今回、新たに危険度計算を行った結果、全体的な危険度は大きくなりますが、都道府県によっては、低い等地の変更になり、基本料率が下がりました。
表2 等地区分
| 改正前 | 2017年1月 以降 |
都道府県 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩手、秋田、山形、栃木、群馬、富山、石川、福井、長野、滋賀、鳥取、島根、岡山、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島 |
| 2 | 北海道、青森、新潟、岐阜、京都、兵庫、奈良 | |
| 2 | 宮城、福島、山梨、香川、大分、宮崎、沖縄 | |
| 3 | 愛知、三重、大阪、和歌山、愛媛 | |
| 3 | 茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、徳島、高知 |
2回目以降の基準料率の引き上げは、今後の各種基礎データの更新などの影響を踏まえて行われる予定です。
まとめ
以上、地震保険料の値上げの要因についてみてきました。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
地震保険の基本情報
知っておきたい地震保険のアレコレ!
今すぐ相談したい方はこちら
![]()